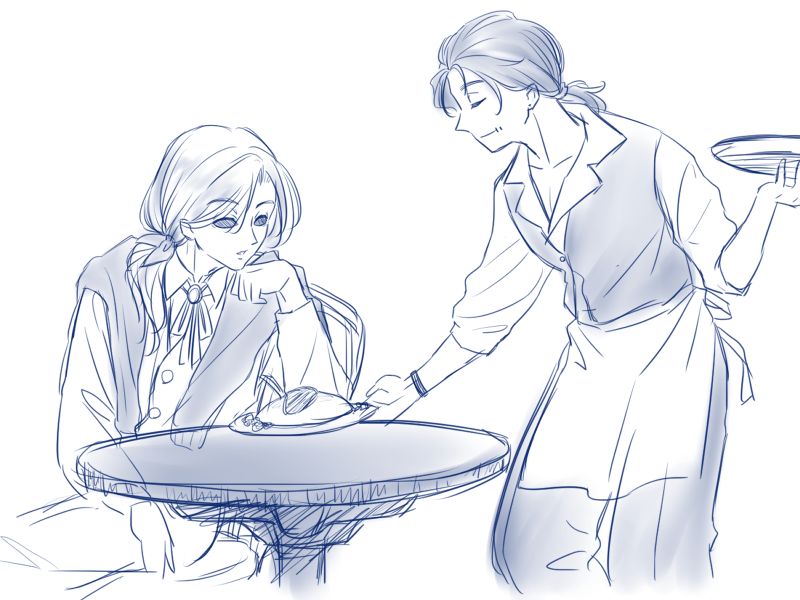第五人格のバレンタインコラボカフェから生まれた妄想。与太話。
【登場人物】傭兵/探鉱者/写真家/占い師/一等航海士/他
フルゴは出ません。相傭→探傭。ニュアンス写傭?
ナがとにかく弱ってなよなよしている。カッコイイ傭兵はいない。
死んだ相の面影と思い出に囚われて色々弱くなっている傭(荘園の記憶無し)。
以前より気楽な人生を送っていたけど傭と再会して狂わされていく探(記憶あり)。
弱った傭を保護したのはいいけどちょっと持て余して面倒になりつつ探傭を見守る写(記憶あり)。
航海士として順風満帆な人生を送ってる一等航海士(記憶?)。探のビジネスパートナー。
一般男性として人生楽しんでる占(記憶?)。素知らぬふりで色々助言したり探傭を見守ってる。
想定外に長くなっちゃったので前後編に分けました。前編では探がほぼ出てきません。どちらかというと相傭・写傭・占傭っぽさが強めかも。
ただの妄想を文字に起こしただけの駄文。読み難さが限界突破してる。
それでもOKという方はどうぞ~
プロローグ
あの奇妙な荘園で起きた事件からどれくらい月日が流れたかは知らない。そんな荘園の話など誰も知らないし口にする者もいないから、ひょっとしたらそれ自体が夢か幻か、はたまた別の世界の出来事だったのかもしれない。
そもそもナワーブ・サベダーにはそういった”以前の自分”の記憶が丸きりなかった。辛うじて覚えているのは、どこか遠くの貧しい村で生まれ育った事。寂し気な笑みを湛えた母と思しき女性の面影。銃声と爆音…誰かの悲鳴…泣き叫ぶ声。そして、いつも隣にいた筈の、嘗て相棒と呼び慕い合っていた筈の存在。その消えかけた温もり。
掛け替えのない相棒を喪った時、ナワーブが失くしたのは最愛の彼だけではなかった。子供の頃、思うまま風のように山野を駆けた俊敏な脚も、幾度となく仲間を守り盾となった強靭な肉体も、どんな困難な状況でも常に最善の一手を選び抜き自身を生かした冴え渡る思考力も…
嘗て最強の傭兵と謳われた男を形作る何もかもが少しずつ欠けて失われて、そうして歪なまま壊れてしまったナワーブは自分の戻るべき場所さえも見失って、ただその命の蝋燭が尽きる日まで漫然と当て所なく歩き続けるだけの人形になってしまう。
雨の日も風の日も、ぬかるんだ野道も険しい山道も… もう以前のようには動かなくなった脚を引き摺って歩き続けたナワーブは、いつしか青い海を望む海岸沿いの静かな田舎町に辿り着く。
白い石畳の上でぼんやりと立ち尽くし眼前に広がる青く煌めく水平線を眺めていると、暖かい潮風がボサボサになった髪を揺らし耳を擽っていく。それはまるでいなくなった筈の相棒が囁いているようだった。
『あぁ、海が見たいな。故郷を離れたあの日みたいにさ、大海原に船出していく船を見ていると、いつだってまたあの場所へ帰れるんじゃないかって気がするんだ。』
そう言って笑った相棒の瞳は、眩しすぎる陽光の中で影になってじわりと滲み、消えてしまった。
写真家との再会
街の外れに設けられた展望台は人通りも少なく、街と海と水平線とが一望できる最高のロケーションだった。とりわけ散歩と写真撮影だけが生き甲斐の”御隠居”であるジョゼフにとっては。
彼がその展望台を訪れてそこから見渡す風景を写真に納めるのは季節毎の恒例行事でもあったが、その日、みすぼらしく小さな見覚えしかないその人影がそこに佇んでいたのは、全くの偶然だった。
その後ろ姿を眼にした瞬間、元荘園の”狩人”であったジョゼフの脳裏に当時の記憶と何とも言い知れない感情が蘇る。荘園において純粋な武器による攻撃では最強と謂わしめたジョゼフの攻撃を限界まで受けても尚立っていられたのは、あの小さくすばしっこい傭兵と赤ら顔のふざけた一等航海士だけである。
今、目の前にある捨てられた人形と言われても疑わないようなボロボロの背中から感じたのは、当時のあの傭兵から感じた忌々しさと同様― いや、むしろ全く同じ感覚だった。
「まだ生きてたんだ。なんでこんな所にいるの、きみ。」
自身の無様な記憶と感情など短い溜息と共に吐き出してしまえば、残るのは美しく優雅なフランス貴族だけだ。仇敵と思しきその薄汚れた緑色に声を掛けることにも躊躇いはない。
―が、しかし。僅かに遅れて振り返ったその顔は、その眼は… 記憶の中で見た鋭く光るあの青緑とは似ても似つかない、くすんだ色をしていた。
拾われた傭兵
ジョゼフに拾われて1週間程経った頃、ナワーブはやっと己が誰かに保護されたらしいという事に気付く。
ジョゼフと名乗ったその男はあの海沿いの街から少し離れた土地に小さいながらも立派な邸宅を構えて隠居暮らしをしているらしかった。街でも顔の利く有力者で”ご隠居”となればそこそこ高齢の筈だが、外見はどう見ても20代前後にしか見えない。
館での暮らしに少し慣れた頃、何の気なしに歳を訊ねたら予想外の答えを聞かされ「年齢詐欺にも程がある」と思わず口走ってしまった。
「生まれ変わっても童顔の君に言われたくないよ」
…とは、どうも不服を買ったらしいジョゼフからの謎の文句だ。自身が童顔であることはよく言われるが、『生まれ変わっても』とはどういう意味だろうか。その時は一瞬、頭の上に疑問符を浮かべただけで、すぐにその疑問も忘れてしまった。
疑問と言えば、そもそもジョゼフは何故、見ず知らずの自分を館に連れ帰って保護したのだろうか。よく覚えていないが、初めて会った時の印象ではあまり良く思われていなかったような気がするのに。
何日も飲まず食わずで痩せ細り、殆ど死にかけだったナワーブを連れ帰ったジョゼフは、まるで拾った野良犬を世話するが如く風呂に入れ、綺麗な服を着せ、温かな食事と寝床を提供してくれた(無論やったのはジョゼフ本人ではなく使用人たちだが)。
保護された当のナワーブは、自分がおかれている状況も、何故そうなっているのかという理由もわからなかったし、考える気力もなかった。だから冗談でも大袈裟でもなく、拾われてきた野良犬や野良猫かのようにただ黙ってされるがままボロボロになった身体を癒されてしまったのだ。
ぬくぬくとした毛布に包まれると嫌が応でも身体は休息を求め、数日は夢も見ない程に深く眠り込んでしまった。あまりにも長い事目を覚まさないので使用人たちは医者を呼んだ方が良いのではないかと心配したらしいが、ジョゼフは「これはそう簡単に死んだりしないから必要ないよ」と、少し顔を見ただけでまた趣味の写真撮影に戻ったという。
目が覚めると体力はかなり回復していた。体力が戻ると腹は減るし、腹が満たされるとまた眠くなる。健康的な生活によって身体が元の調子を取り戻すにつれ、朦朧として霞がかっていた意識もハッキリとしてきた。
…けれど、思い出すのは自身にとって半身のような存在だった相棒を喪ったという残酷な事実だけだった。それに気が付くとナワーブはまた考えることをやめて、ただ耳に届く潮騒に目を閉じ、流れる日々に身を任せるだけの抜け殻になってしまった。
「あぁ、ほんとうに。どうして俺はまだ、生きてるんだろう?」
占い師との再会
ジョゼフに保護されてから数週間。ナワーブは未だ生きる目的を見つけられずにいるものの、平穏で退屈な日々に慣れていく。生来、怠けるより動き回って人に尽くす方が好きな性分だったので、体力が戻るとすぐに館の使用人たちを手伝ったり、街へ買い物へ行くついでに困っている人がいると手助けするようになり、すぐ街の住人たちとも打ち解けた。
初めのうちは、ジョゼフがどこからか拾ってきた素性もよくわからない傭兵上がり(らしい)という事で多少警戒されてはいたが、この頃のナワーブに嘗てのような鋭さや覇気はなく、その童顔に上乗せされた温厚そうな雰囲気と困っている人がいれば考える間もなく手を差し伸べるお人好しな性格のおかげで、すぐに街の人々から可愛がられるようになっていった。
何か頼まれごとをされると断れず、自分にできる事ならとりあえず協力するという姿勢から”なんでも出来る気立てのいい兄ちゃん”と思われているが、実際のところ以前のように思い通りに身体を動かせているわけではなかった。負傷した片足は必要以上に早く歩けないし、筋力も衰えているのか重い物を持ち上げるのに苦労する。周囲のちょっとした物音や気配にもかなり鈍くなった。
しかし、そんな嘗ての”傭兵”の姿など街の住民は知る由もなく、階段や坂道をゆっくり歩いたり立ち止まってぼんやり海を眺める姿を見ても「呑気な人だ」と微笑むだけ。
そんな住民たちの中で、周りと同じようでいて少し違った接し方をしてくれたのがイライ・クラークだった。彼もナワーブと同じように街の外からやってきて、今はジョゼフとは別の貴族の屋敷でお手伝いさん?のようなことをして生活しているらしい。いつも不思議な目隠しをしているせいでやはりナワーブと同じように色眼鏡で見られていたが、外見に反して朗らかで親切な人柄から今では元々街の住民だったのではないかと思う程打ち解けている。どうやらお屋敷の令嬢と恋仲になったとかで、街のお年寄りたちはまるで孫の恋路を見守るように進展はないのかと口々に噂している。
そんなイライとナワーブが初めて言葉を交わしたのは、ナワーブが買い物がてら例の展望台へ立ち寄ろうとしていた時だった。その日はまとめて買ったワインボトルが少し重かったのか、いつもより脚が痛んで展望台へ続く坂の下で座り込んでしまった。そこへ、チリリンと軽やかな自転車のベルを鳴らしてイライがやってきたのだ。
「やぁ、ナワーブ! 大変そうだね。よかったら乗せようか?」
「…お前の体力じゃ、俺を後ろに乗せてこの坂を上るのは無理だろう」
そう口にしてから2秒…3秒… じわじわと自分の言葉に違和感を覚えて、元々噛み合わせの悪い歯車のようだった思考が完全に停止してしまう。
何故、この男では自分を乗せて坂道を上るのは無理だと思ったのだろう。見たところ決して屈強とは言えないが普通の成人男性だ。小柄なナワーブに比べれば背丈もある。それにそんな、まるでよく知った古い友人のような返事を自然と返せてしまった事が不思議でならない。
何より、今この男は自分の名前を呼んでいた。街で少し噂になって知っていたせいかも知れないが、それにしても初対面の筈の相手からあんな親し気に呼ばれるものだろうか。
「ははは、そうだね。きっと私には無理だ。なら一緒に歩こうか。この先の展望台へ行くんだろう? その荷物を貸してごらんよ。」
固まったまま動かないナワーブの代わりに目隠しの男が言う。その言葉はスラスラと淀みなく、まるでナワーブのことを何でもわかっているかのようだ。不思議な男だと思う。初めて会った筈なのに本当に昔からの友人なのではないかと錯覚させる程に自然体なのだから。
「あぁ… ありがとう。」
ややあってからナワーブはやっと思考の歯車を再起動させ、のろりと立ち上がりながら抱えていたワインボトルの入った紙袋を男へと差し出す。その間も、男は穏やかな笑みを口元に湛えたままナワーブが動き出すのを待っているようだった。
「これは重いね。さぁ行こう、歩けるかい?」
「…あぁ」
ナワーブから渡された紙袋を自転車の前籠に積むと男は少し重くなった自転車を押しながら先に立って歩きだした。ナワーブもそれに続き、まだ少し痛む脚に負担をかけないようゆっくりと坂道を上っていく。
ナワーブの片足が不自由なのを知っているのか、男はナワーブの歩調に合わせ離れすぎない距離を後ろを振り返りながら進んでいく。
こちらを振り返るということは、目隠しをしていてもちゃんと眼で見ているということなのだろうか。謎めいた言動といい、本当に不思議な男だ。
「ナワーブは相変わらず優しいね。本当は訊きたいことがいっぱいあるのに、私を気遣って黙っていてくれる。」
「・・・・・・」
気遣っている、というのは大袈裟だ。実際のところは単によく知らない相手に質問するのが気が引けるだけだ。しかし、こうまで言われてしまうと訊かないでいる方が逆に難しい。
「…アンタ、俺のことを知っているみたいだが、どこかで会ったか?」
そう口に出して漸く気が付く。この男だけではない。ジョゼフもそうだった。初対面の筈の自分をわざわざ館に連れ帰って世話を焼いて… それに時々、昔からナワーブのことを知っていたかのような発言もしていた。
男は口元に浮かべた笑みはそのままに、こちらに向けていた顔を少しだけ前に向き直して答える。
「いいや、今日初めて会ったよ。でも君のことはよく知っている。ずっと昔からね。」
「…何を言ってるのかわからない。」
男から返されてきた答えは、ただナワーブの疑問を大きくしただけだった。そうだ、ずっと考えることを放棄していたけど、この街へ来てからというものわからないことばかりなのだ。
街でたまに会う建築家だという爺さんや、爺さんの雇い主だというどこかの女王様にも見紛うような貴婦人。その友人らしい東洋風の美女。爺さんと一緒におかしな機械の話を熱心にしていた図体のデカい男。街外れにアトリエを構える兄妹…
上げたら切りがないが、皆 何故かナワーブの事を知っているかのように、ナワーブの知らない話をしていた。
「・・・・・・」
久しく考えることを止めていた思考回路が一度に押し寄せた疑問符の波に悲鳴を上げている。また考えるのを放棄したくなって痛みを訴える頭を抱えて蹲ろうとすると、そんなナワーブの耳元をヒュウッと静かな風切り音が掠めていった。
その音にハッとして顔を上げてみると、いつの間に坂を上り切ったのか展望台の石垣に自転車を立て掛けた男が、オレンジに染まり始めた空を見上げて何やら片腕を掲げていた。するとそこへ、視界の端からすーっと滑り込むような軌道を描いてフクロウと思しき一羽の鳥が舞い降りてきたのだ。
「…フクロウ…?」
見たところ飼い慣らされた鳥なのだろうか。男の腕に静かにとまるその姿は優美なもので、閉じられた片目はどことなく男と同じような謎めいた雰囲気を感じさせる。
「私の一番の友達でね。彼女も君のことをよく知っているそうだよ。」
男がそう言うのに合わせてフクロウの開かれていた片目がこちらへと向けられる。ガラス玉のように見るものを映すその瞳に捕らわれ、ナワーブは息を詰まらせた。
何故だろう… フクロウのその眼を、その中に映る自分の姿を見ていると、確かに何かが呼び覚まされるようで、酷く胸がざわついて苦しくなる。本当に自分の知らない別の自分がいたのだろうか。一体どれだけ自分の知らないことがあるというのだろうか。――どれだけ、忘れているのだろうか。
ガラス玉の中に囚われている自分を見ていられなくなり、ふいっと視線を逸らすとその先にあの水平線があった。今は夕焼けのオレンジとそこに混じり合う紫に彩られ、空と海の狭間に白い光がキラキラと散りばめられて輝いている。
『あぁ、海が見たいな―』
またアイツの声が聞こえた気がした。何よりも愛しくて、恋しくて、けれどどんなに求めても二度と聞くことのできない声。
その声ももう、以前のようにハッキリと思い出すことさえ出来ない。あんなに忘れたくないと… 失いたくないと願っていたのに。自分の半身と思っていた愛しい相棒の面影すら忘れて、こんな空っぽになった自分を、一体何が、誰が”ナワーブ・サベダー”という存在を証明してくれるのだろう。
「俺は… 知らない。わからないんだ。……失くしてしまった… 全部…っ ――」
気付かぬうちにみっともなく涙を溢して嗚咽していた。頬を伝って流れ落ちる水滴が白い石畳に染み込んで歪な模様を広げていく。そのぼやけた曖昧な輪郭は少しずつ形を失っていくナワーブの大切な記憶そのものだった。
―― ピューィ…
不意に、高く澄んだ鳴き声が響いて、沈みかけたナワーブの意識が引き戻される。ぐしゃぐしゃに濡れた頬のまま見上げると、頭上をあのフクロウが飛んでいた。美しい夕焼け空の下に大きな翼を広げて、音もなく静かに、ゆっくりとナワーブの上を旋回している。
さっきはあのフクロウの瞳を見て恐ろしささえ感じていたのに、今ナワーブの眼に映るその風景は何故だか悲しみや不安で押し潰されそうになっていたナワーブの心に不思議な安心感をもたらした。
―― 動かないで、手伝うよ!
『 援護するから……一緒に… ――ナワーブ!! 』
「―――…!」
一瞬、羽ばたくフクロウの影の中に戦場で隣り合った相棒の勇ましい背中が見えた気がした。いや、あれは本当にアイツだったのだろうか? それにあの声は… 低く太く、少しくぐもっていて、しかしハッキリと自分の名前を呼んでいた。あの声は…―
「……今の、声…?」
もう一度確かめたいと思っても、あまりにも短く頭に響いたそれは残響さえも風と波の音に掻き消されてしまって、たった今聞いたばかりの筈なのにもう思い出すことすら出来ない。
呆然とするナワーブの頭上でフクロウは広げた翼を翻らせるとまた目隠しの男の元へと舞い戻り、大きかった翼を折り畳んでちょこんと男の肩に留まった。
「ごめんよ、辛い思いをさせたかな。でも少しはスッキリしただろう? 君の不安を取り除くのは昔から彼女の方が上手なんだ。」
男は相変わらずナワーブには理解できないことを口にしながら肩に留まったフクロウのふわふわとした羽毛を撫でてみせる。言っている意味はわからないが、先程まで頬をぐしゃぐしゃに濡らして泣いていたナワーブの心からあんなに重苦しかった不安感がなくなり、すっかり落ち着きを取り戻したのは事実だ。
冷静になってやっと自分が泣いていた事に気付くと急に恥ずかしくなって、ジョゼフに貸し与えられた綺麗なシャツの袖でごしごしと頬を拭った。
「君は全部失くしてしまったと言っていたけど、何一つなくなってはいないよ。私やこのフクロウや、君を知る皆がちゃんと憶えている。それに―…」
ナワーブが涙を拭いている間も男はフクロウを撫でつつ穏やかに宥めるような口調でそう語る。…が、少し話したところで言葉を繋げるのを止めてしまった。
「あぁ、やはり言葉だけで君の心を癒すのは難しいな。悔しいなぁ。今度こそ君の助けになりたいと思ったのに。」
男は困ったように言って僅かに眉を下げてみせる。それだけで見たこともない目隠しの下の眼が人の好さそうな優しい表情をしているのだとわかった。
「いいんだ。ありがとう。きっとアンタは良い友人だったんだろうな。憶えていないのが惜しいよ。」
「それはこちらの台詞さ! ナワーブには本当に感謝しているんだから。こうしてまた会うことが出来て嬉しいよ。」
最初に声を掛けられた時の奇妙な印象から一転し、清々しささえ感じる声で言って男は手を差し出してきた。同時にその肩に留まっていたフクロウがピュイッと短く鳴く。ナワーブもそれに応え、差し出された手を握り返した。
「イライ・クラークだ。改めてよろしく、ナワーブ。」
「あぁ、よろしくな。イライ。」
「…安心していいよ、ナワーブ。きっと君の安らぎは、もうすぐやって来るから。」
ジョゼフの提案
「少し前から空き家になってる店があるだろう? あそこでカフェでも営んでみなよ。」
そんな話をジョゼフから切り出されたのは、ナワーブが街にやってきて三か月が経った頃だった。季節は春から夏へ入ろうとしており、田舎とは言え海のすぐ傍にある街にはこれから少しずつ観光客がやってくる。一年で一番街が賑やかになるシーズンだとイライは言っていた。
「カフェなんて… なんでそんな、急に。出来るわけないだろう、俺なんかに。」
置いておくのが面倒になったから出ていけ、という通告ならいつされてもおかしくないと考えていたが、予想もしなかった話に動揺して思わず悲観的な返事をしてしまった。こういう言い方は好かない男だったと気付き、数秒前の失言を悔やむ。
案の定、ナワーブの返事はジョゼフの機嫌を損ねたらしかった。
「やってもいないのに無理だとか、そういう考えは好きじゃないな。頼まれれば”化け猫”でも”探偵”でも演じてみせた万能傭兵が、接客業ごとき出来ない筈がないだろう。」
「なんだよ化け猫って、そんなめちゃくちゃな仕事をした覚えはない!」
ここ暫くでは珍しく声を荒げてしまった。恐らくいつもの”ナワーブだけが知らないナワーブの話”なのだろう。慣れてきたとは言え、ジョゼフに言われると何故かいつも調子を狂わされる。どうもこの男とは相性が悪いらしい。
しかしながらナワーブを揶揄ったことでジョゼフの機嫌は多少上向きに戻ったようだ。にんまりと意地の悪い笑みを浮かべている。ナワーブはガシガシと頭を掻いて溜息を吐く。緩く束ねた長髪が余計に乱れてしまった。
「…なんでカフェなんだよ。出ていって欲しいならそう言えばいいだろう。すぐにだって出ていける。」
「私をそんな無責任な男だと本気で思っているなら、それこそ心外だね。今日までここに置いて世話してやった恩人に対して失礼だと思わないのかい?」
「・・・・・・」
本当にこの男とはつくづく相性が悪い。こんな風にジョゼフに言い負かされると、ナワーブはもう一言だって反論できなくなるのだ。
拾われて一つ屋根の下で暮らすようになってから三か月。常に一緒というわけではない(むしろ一緒にいない時間の方が多い)し、気まぐれで意地の悪いところもあるが、この男が悪人でないことを理解するには十分過ぎる時間があった。今だって、”世話してやった”など恩着せがましいことは微塵も思っていないくせに。
『ならどうして』 …と、口には出さずとも不貞腐れたように俯くナワーブに、ジョゼフははーっと大袈裟な溜息を吐いて見せた。
「そういう陰気な顔で傍にいられると、いい加減鬱陶しいんだよ。こっちまで気が滅入ってしまう。これから観光客も増えて忙しくなるし、自分で店でも開けばその陰鬱な表情も少しはマシになるだろう。」
ぐうの音も出ない正論を言われて増々何も言い返せなくなってしまった。要は未だに塞ぎ込んだまま立ち直れないナワーブ自身の為に心機一転して自活してみせろ、という事だ。
イライと友達になったことや街の住民と付き合う中で少しずつ立ち直っているつもりでいたが、ジョゼフには到底そうは見えなかったらしい。実際のところ、ナワーブが明るく振舞えているのは表面上だけだ。心の奥底では未だに相棒の死や日に日に薄れていく記憶と向き合うことに怯え、逃げている。
自分で店を開き、辛い思い出や感傷に浸ることも忘れる程に忙しい生活を送れば、そのうちに悲しみや寂しさなんていう感情も消えてくれるのだろうか。
…消してしまってもいいのだろうか。
「……少し、考える時間をくれないか。」
ジョゼフは返事の代わりにナワーブの淹れた紅茶を一口啜ると、また短く息を吐いた。
イライの助言
「カフェ経営? いいじゃないか!ナワーブにぴったりだと思うよ。」
館の使用人に頼まれたお遣いの道中、いつもの自転車を押しながら隣を歩くイライは疑いなど微塵もないという晴れやかな笑顔(当然いつもの目隠しで眼は見えないが)で即答した。
「……化け猫でも演じられる俺になら、か?」
「ははは。あったかもしれないね、そんなことも。」
わかってはいたことだが、ジョゼフの質の悪い冗談と思いたかった話をいともアッサリと肯定されてしまい、ナワーブはがっくりと肩を落とした。
「…ナワーブは、”以前の自分”については気になっているのに、教えてくれとは言わないんだね。」
「・・・・・・」
それは”今の自分は知らない別の自分の記憶”があるらしいとイライに聞かされてから、ずっと自分自身でも問い続けてきた疑問だった。自分の知らない自分のことが気にならない訳ではない。でも知ろうとすると、自分にはない筈の記憶を探ろうとすると、何故だかとてつもない恐怖に襲われてそれ以上考えることができなくなった。
きっと、自分の知らない自分の記憶を手に入れるのと引き換えに、朧気になった相棒の記憶が失われていくのが恐いのだ。
「まぁ慌てることはないよ。それにカフェのこともね。心配せずともナワーブが望めば、全て上手い方へ向かっていくさ。」
鼻歌でも歌い出しそうな呑気な調子でそうイライが言えば、彼のベレー帽の上に留まっていたフクロウまでもがピュイッと軽やかに鳴いて呼応してみせた。
回答の日
ジョゼフからの提案に答えを出せないまま一週間が過ぎようとしていた。ナワーブは今日も朝から使用人のお遣いやら街の住民の手伝いだと言い訳をして、一日の殆どを街の中で過ごした。
しかし、それにとうとう業を煮やしたのか、夜になってジョゼフから直々にお呼び出しを食らってしまった。ナワーブは一度厨房へ行って使用人が用意したティーセットを受け取ると、それこそ死地へ向かう兵士のような表情でジョゼフの部屋の扉を叩いた。
「考える時間は十分に与えた筈だよ。それにあの占い師にも相談したんだろう?」
ジョゼフの言う”占い師”とはイライのことだ。確かに人の心を見透かしたようなことを言ったり、街の人々に頼まれて占いのようなことをすることもあるそうだが、彼の仕事はあくまで貴族屋敷の”お手伝いさん”だ。何故そんな風に呼ばれているのかナワーブにはわからないが、きっとそれもナワーブの知らない彼らの記憶に関係しているのだろう。
「で。彼はなんと言っていたんだい?」
「…え…… あぁ、『きっと上手い方へ向かう』… と。」
テーブルに用意された紅茶を啜りながら「相変わらずあの占い師の言葉は曖昧なことばかりだね」と呆れたように言うジョゼフ。しかし特に気を悪くしている風ではなく、むしろ安堵しているようにすら見える。
「ともかく、彼にもそう言われたのなら、いい加減君の決心も着いただろう? それともまだ何か問題があるのかい?」
ティーカップをソーサーに置いたジョゼフはこれ以上言い逃れはさせるまいとばかりにナワーブの眼を真っ直ぐに見据えてくる。まるで鋭利な剣の切っ先を喉元に向けられているような居心地に、ナワーブも観念して声を絞り出した。
「……もし、やっぱりダメだと思ったら、その時は逃げてもいいか? またここに置いてくれなんて言わない。迷惑かけないように、一人で行くから。」
「…かまわないよ。君がそうしたいと言うなら引き留める理由もないしね。好きにすればいいさ。」
ナワーブの答えを聞いてまたヘソを曲げるかとも思ったが、ジョゼフの表情は読めない。先程まで向けられていた刺すような視線も今はまた手元のティーカップへと落とされ、再び紅茶の味に瞼を伏している。
とりあえずその場は凌いだかと張り詰めていた緊張の糸を解き、トレーを片手に退室しようと踵を返すナワーブ。その背中にまたジョゼフが声を投げかける。
「そういえば君、髪の手入れはしているかい?」
「は?」
突拍子もない問い掛けに思わず眉をひそめて振り返る。と、ジョゼフは手にしていたティーカップをテーブルに置いて立ち上がり、去りかけたナワーブの傍まで歩み寄ると緩く結われた後ろ髪の束を摘んでみせた。
「…やっぱり、また傷んでいるじゃないか。ちゃんと毎日入浴しているんだろうね?」
「してる!髪だって洗ってるし、寝る前にちゃんと乾かしてる」
「オイルは?」
「・・・・・・」
「はぁ…―― ここへ来たばかりの頃、身嗜みはきちんとするように言った筈だね。理解できていないのなら、執事にまた一から教えてもらおうか。」
「いい、いい! わかったよ、自分でやるから!」
ナワーブを見下ろしつつ掴んだ毛を指先で弄ぶジョゼフの手を払いのけると、みっともなくそう叫んで距離をとる。
「なぁ、なんだってそんなに俺に構うんだよ。寝床や食事の世話をしてくれてるのは感謝してるけど、着るものや髪にまであれこれ言う必要ないだろ?」
「何を言ってるんだい。ここにいる限り、君の主はこの私なんだよ。私に仕えるなら、それ相応の格好をしてもらわなければ困るのだよ。」
言いながらジョゼフは自身の艶やかな長い髪をさらりと手で流してみせる。そのあまりにも麗しい(とても〇十歳とは思えない)姿を見せつけられて眩暈がするようだった。
アイツではない誰か
ジョゼフの館で暮らすようになってからというもの、使用人たちと同じ浴室を使って毎日入浴を行うことが日課―というより、それがナワーブに課された義務の一つになった。
ジョゼフは「薄汚いネズミみたいな格好で館をうろつかれるのは困る」だとか、さも迷惑であるかのように言うが、実際にはそれだけでないことはナワーブにもわかっている。いや、必要以上に外見に拘るジョゼフのことだから、汚い格好で居座られるのが許せないというのも本心なのだろうが。
砂埃と泥、そして数え切れない程の人の血に塗れ、ボロボロに擦り切れたくすんだ緑色の上着を剥ぎ取られ、代わりに貸し与えられた服は、ナワーブが今まで身に着けたどんな服よりも上等な肌触りの良い生地で織られていて、洒落た花の模様と身体の小さなナワーブには少し余裕のあり過ぎるゆったりとした作りがこそばゆく、最初はなんだか落ち着かなかった。
髪型も、今までは戦場での邪魔にならないようきつく後ろで縛っていたのを、緩くまとめるだけにするように言い付けられ、その上ヘアオイルで丁寧に手入れまでされてしまった。
ジョゼフ曰く、
「あんな身体を締め付けるような窮屈な服装ばかりしているから心まで余裕がなくなるんだよ。それに髪だって、こんなにきつく縛ったら傷んだ毛が余計に切れてしまうじゃないか。素材は悪くないのにこんな勿体ないことをするなんて愚の骨頂だよ。」
…とのことらしい。
自分のどこがそんな評価に値するというのかナワーブにはさっぱりわからないが、ジョゼフは自分が良いと思ったものを粗末に扱うのは一等許せない質らしい。その時はやけに不機嫌そうに怒っていた。
熱いシャワーを頭から浴びると、一日中海辺の街の中で過ごしてベタついていた肌や髪が綺麗に洗い流されていくのがわかる。多少の怪我や汚れなど日常茶飯事だった以前の生活では考えられないことだが、こうして身形を整え清潔なシャツに腕を通して生活していると、それだけで常に曇天の空のようだった気持ちにも晴れ間が差し、ほんの少し視線を上げて生きていられるような気がした。
清潔を保つことは心身の健康にも繋がるのだと、顔も名前も思い出せないどこかの医者が言っていたような気がするが、あの言葉は確かに間違いではなかったと痛感する。きっと腕の良い信頼できる医者だったのだろう。
足元のタイルの床に薄い水溜まりを作り排水溝の中へと流れ落ちていく湯を見つめていると、ふと戦場での記憶が蘇ってきた。
前線から遠く離れた僻地を少数の仲間たちと共に進行していた時のことだ。敵の気配もなく静かな夜、ナワーブは相棒と二人で野営地を抜け出すと月明りが照らす野道を足音もなく駆け、道中で見かけた川へと向かった。
戦場では身綺麗でいられることなどまず有り得ないが、不衛生であってもならない。不衛生な身体は細菌の温床となり、怪我や病気を悪化させる。それは自分だけでなく仲間を苦しめ戦況を悪化させる原因にもなるからだ。
その為、状況を見て使えそうな水がある時には、仲間たちと交代で見張りをしながら最小限の水で汚れた身体を濯ぎ、傷口の泥を落として血を洗ったものだ。
その日は月の明るい晩で地理的にも奇襲の心配はなかったが湯を沸かす程の余裕は流石になく、川岸で着ていた衣服を脱ぎ捨てると素っ裸になって二人で川面に飛び込んだ。冷たい水に身を震わせ寒い寒いと悲鳴を上げながらもお互いの頭に水を浴びせて笑い合った。
そんな光景を思い出して、ふっと口元が緩む。
……だがその時、確かに思い出せていた筈の相棒の笑顔に突然、割れた鏡のようなヒビが入り、その深く暗い隙間から別の誰かの影が覗いたのだ。
『 ――ナワーブ 』
ひび割れから覗くその影は相棒とは明らかに違う声でナワーブに呼びかけてくる。それは以前、イライと話した時に聞こえたあの太く低く、くぐもった声だった。
あの日からあの声は時折、相棒との思い出に混じって聞こえるようになり、次第に鮮明になっていった。そしてハッキリと聞こえるようになるにつれ今度はその声の主と思われる影もが見えるようになってきたのだ。
しかしその声と影が形を持つようになると、それと入れ替わるようにして相棒の姿は増々薄らいでいく。
ナワーブは濡れた髪を振り乱しながら頭を振ると、打ち付けるシャワーの湯の中で俯きぎゅっと目を瞑った。
(ダメだ、来ないでくれ。俺の名前を呼ばないでくれ。頼むから、アイツの記憶を奪わないでくれ…)
新装開店 新しい生活
それからまた三週間程が経った頃、海辺の田舎町にある路地裏の空き家に小さなカフェがオープンした。
以前は老齢の女性が一人で暮らしていたという店舗はそれ程大きくなく、厨房に繋がるカウンターと数席のテーブルが収まるホールは、嘗て女性が一日の殆どを気ままに過ごしていたダイニングに急遽カウンターを取り付けて改装したものだ。改築には例の建築家が一役買ってくれた。
建物の表半分は店として利用されているが、厨房を挟んだ奥は居住スペースとして以前のまま残され、ナワーブはそこで一人で暮らすことになった。
路地裏という立地は決して人通りは多くないものの落ち着きがあり、静かに海を眺めながら食事を楽しみたい客には打って付けの店とも言える。何よりカフェのマスターであるナワーブにとって、大勢の客で賑わうよりも地元民や少しの客を相手に商売するこじんまりとした店の方が望ましい。
「なるほど、あの荘園を管理していたというだけのことはあるね。あの爺さんもなかなかやるじゃないか。」
まだ真新しさは残るもののしっかりと客を迎える準備を整えた店内を見渡し、ジョゼフは納得したように頷いて見せる。いよいよ開店を明日に控えたその日、慌ただしく最後の準備に追われているナワーブのところに誰よりも先にやってきたのがカフェのオーナーという特権を持つこのフランス貴族様だ。
「見ていくのは勝手だが、何も提供できないぞ。まだ開店前なんだ。」
ナワーブは入ってきたジョゼフに眼を向ける暇もなくカウンターの中で忙しくしている。
既に観光客で賑わっている時期とはいえ、特に新装開店の宣伝をしている訳でもないし、人目に付かない路地裏の店だ。初日から客が押し寄せるようなことはないと思うが、備えるに越したことはない。それにまだ飲み物も食事も品数の少ないメニューだが、少ないからこそ手抜きがあってはならない。
生来 真面目で一度やると決めたことは完璧にこなそうと努力するのがナワーブ・サベダーという男だ。ジョゼフの目論見通り、こうして店に立っている間はその横顔に陰りはなく、活き活きとして働いている。
「かまわないよ。私の楽しみは君の手料理じゃない。こうしてこの店の記録を収めることだからね。」
そう言うとジョゼフは持ってきた写真機を店の隅にセットし、店内と小さなアーチ窓から覗く真っ青な景色を四角い枠の中に切り取って写真に収めた。
店内に置かれた家具や雑貨、食器類は以前の家主だった女性が使っていたものと、カフェを始めるにあたりジョゼフが新しく取り寄せたものとが混在し、牧歌的でありながらどこか小洒落たセンスの光る一風変わった雰囲気を醸している。
そして何よりテラス席からの展望が最高だ。それ程広くはないが日当たりの良いテーブル席に座り、一面に広がる青い海を眺めながら飲む紅茶の味はきっと格別だろう。
ファインダー越しに見えるその風景を眺めながら、ジョゼフはまた一つ楽しみが増えたとにんまり笑みを浮かべた。
「折角だから少し味見していってくれないか。」
不意に声を掛けられ顔を向けてみると、先程までこちらを見向きもせず準備に勤しんでいたナワーブが、湯気の立つティーカップをカウンターに置いて頬杖をつきこちらを覗いていた。
「何も提供できないんじゃなかったのかい。」
「味も保証できないものを客に出せないだろ。これも準備の一環だ。」
カウンター席に座り置かれていたティーカップに眼を落すと、そこには淡い茶色の液体がほんの僅かにゆらめきながら温かな湯気を立ち上らせていた。
「ミルクティーかい?」
「チヤだ。俺の故郷の飲み物 ―…だと思う。もうずっと飲んでいなくて、味も作り方もハッキリ覚えていないんだ。」
バツの悪い様子でそういうナワーブに対して「ふぅん」と素っ気なく応え、ティーカップの取っ手を摘むと躊躇いもなくそれに口を付けてみせる。カップを傾けた瞬間、ふわりとしたスパイスの香りが鼻腔へ届き、広がった。
「……随分甘いね。」
数秒、眼を閉じて舌に広がる味を確かめるようにしてからジョゼフが口にした感想は、そんな短くシンプルなものだった。表情は変わらずいつもの読めない眼で揺れるチヤの表面を眺めている。
良いとも悪いとも言えない評価だった筈だが、ナワ―ブにはそれでもかなりショックだったようだ。わかりやすく沈んだ顔で肩を落としている。
「ダメか… 目新しいメニューなんて、これくらいしか思いつかなかったんだがな。」
「べつに、これがこの店の味だというなら、このままでかまわないじゃないか。甘いとは思うが私は嫌いではないよ。」
ナワーブを慰めているつもりなのか、それともただ本心を言っているだけなのか。ジョゼフはそう言うとまたティーカップに指をかけ、もう一口チヤを啜ってみせた。
「文句を言う客がいれば、レモンでも少し絞ってやればいいさ。案外、この味で店が評判になるかもしれないよ。」
翌日、ついに開店したカフェには初日から長蛇の列ができ――… なんてことはなく、ナワーブの考えていた通り、初めはイライや地元の顔見知りたち、そして数組の観光客がやってきた程度で何事もなく終了した。
やはり提供できる料理も少ない為、”一度は行きたい人気の店”となる気配は永久になさそうだったが、しかしながら店の雰囲気とマスターが作る風変りなお茶の味が物好きな観光客に受け、奇跡的にクレームを付けるような客は殆ど現れなかった。(後に流れた噂によると、少し手のかかりそうな観光客に声を掛けて回る目隠しの男がいたとか…)
接客などしたことがないと語っていたマスターはオープン当初こそ苦戦していたようだが、持ち前の器用さと勤勉さで上手いこと店を回し、商売はすぐ軌道に乗った。まだ観光客たちがベッドの中で寝息を立てているような早朝に掃除用具を持ちテラスに佇むマスターの姿は、街の住民にとって見慣れた馴染みの風景となっていった。
…しかし、毎朝テラスに立って海を眺めるその横顔は儚く、未だ憂いを帯びた瞳が水平線の先に何を見ているのかを、誰も知らないでいる。